「会計」「法対応」という言葉を耳にするだけで身構えてしまうIT担当者もいるようだ。苦手意識や思い込みを振り払い、正しく理解することがIFRS対応の基本となる。誤解が生じやすい部分に焦点を当て、ポイントを整理しよう。
誤解1
時期が来れば細則が示されるので、それに準拠すればよい
IFRSは企業に対して細かい会計のルールを「手取り足取り」指図してくれるようなものではない。IFRSはあくまで原理原則にこだわる会計基準であるが、その原理原則は経済実態を反映した時価主義をベースとしたものであり、慣れない日本企業にとってハードルは高い。IFRSは企業に対して「事業実体に即した会計処理」を要求しており、具体的な会計処理については企業ごとに個別に判断を要する場面が日本の会計基準に比べて圧倒的に増える。
IASB(国際会計基準審議会)は、各国仕様の独自解釈基準を出すことを禁じているので、いくら待ちを決め込んでも「これにさえ沿っていれば法対応できる」というガイドラインは提示されない。この点では、既存の日本の会計基準や、J-SOXへの取り組みと大きく様相が異なる。自ら考えて行動を起こさなければ、先には進めない。
固定資産の減価償却を例に挙げれば、多くの企業は税法の償却限度額を会計上も減価償却費として一律に計上するのが一般的だった。このため、同じ工作機械を国内と中国の工場それぞれに導入したとしても、国ごとの税法の規定によって計上額が異なるということが起きていた。ここで、経済活動の実態は不変なのに数字が変わってはおかしいとするのがIFRSである。工作機械として使える年数をはじき出し、実情に即して減価償却することが求められる。つまり、事例ごとの判断が必要となるのだ。この判断によって、財務報告書の数字は変わってしまう。きちんと第三者に説明できる論拠が必要だ。
定められた表の中に間違いなく数字を埋めるのを得意としてきた日本企業だが、今後は自ら考え、理路整然と説明する力が求められる。マインドセットの根本的な変更は想像以上に大変だ。
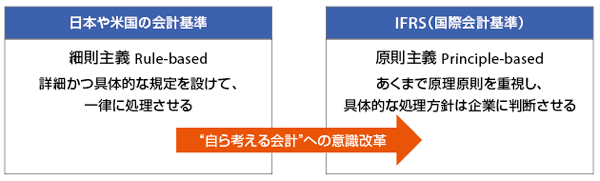
結論IFRSは原理原則を示し、処理は自ら考えなければならない
誤解2
強制適用は2015年、取り組み開始はまだ早い?
企業のビジネス活動の実態を、世界共通の物差しで測れるようにしようというのがIFRSの狙いである。今後、国際経済の中で投資家などから事業内容を正当に評価してもらうには世界標準に沿って財務報告することは不可欠な条件となる。
日本の上場企業に対するIFRSの強制適用は最短で2015年度からとされており、まだ時間があると感じる人もいるかもしれない。ただし、一定の要件を満たす上場企業は早期に任意適用することも可能で、今のところは2010年3月期からとの案が出ている。米国は日本より約1年先行したロードマップを描いており、世界各国に取引先や自社グループ拠点を持つ大企業の中には、積極的にIFRSへシフトを図る例も出てこよう。米国企業を含む同業他社が、一気に動き出すかもしれない。後れを取って「国際感覚のない会社」とのレッテルを張られないためにも、準備を急ぐに越したことはない。特に売上高1000億円超の大企業や、金融機関はIFRS適用の影響が大きくなる可能性が高く、早期に準備を開始した方がよい。
IFRS導入で先行した欧州の企業の経験に照らすと、平均的には3年ほどの準備期間を要した。企業自身が考えて対応を図らなければならない項目は予想以上に多いので時間がかかる。システム面の改修も伴うので、対応プロジェクトは一筋縄ではいかない。
さらにIFRSに沿った財務諸表の開示は2期比較が原則となっている。つまりIFRSの本格導入時には、その前年度の数字を比較対象として開示する必要がある。仮に2015年度にIFRSに移行するなら、2014年度における期首のバランスシートをIFRSベースで作成しなくてはならない。この点にも注意が必要である。
結論早期任意適用も視野に、グローバル企業はすぐに動くべし
誤解3
法対応にのみとどめるのが会社のため
法を順守することを前提に最低限のことをやっておけばよいという消極的な姿勢の企業もあるだろうが、せっかくIFRSを導入するなら会社にとって意義あるものにしたい。「経営管理の質を高める改革の好機」ととらえるのだ。理想論と言われるかもしれないが、いずれIFRSは強制適用されるわけだし、多くの手間やコストも伴う。だからこそ、ムダにすることなく、体質強化に結び付ける発想が必要だ。
多くの企業は、法の下で対外的な財務報告を目的とした「制度会計」と、経営者が業績評価や戦略立案の材料に使う「管理会計」の2つを持っている。経営者が内部で管理している目線で外部公表することを求めるIFRSでは、両者は管理会計寄りに接近してくる。
これはマネジメントアプローチと呼ばれ、例えば事業セグメントの開示においては、事業/商品/顧客/チャネル/地域などの切り口ごとに業績を開示する際、経営トップが実際に意思決定の材料にしている区分に沿ったものにすることを求める。これを実現するには、日頃の会計処理において、セグメントについての情報(フラグ)をきちんと入力するように、業務もシステムも変えなくてはならない。
経営者が利用する意思決定のための材料が、ほぼそのまま外部公表用にも生かせるとなればメリットは大きい。適正な意思決定、経営のスピードアップ、経営の透明性の訴求…。こうした恩恵を受けるためにもIFRS対応を改革のチャンスととらえる姿勢が大切だ。
結論経営管理の道具とする積極的な態度で挑むのが得策
誤解4
経理部門が対応するので、IT部門は無関係
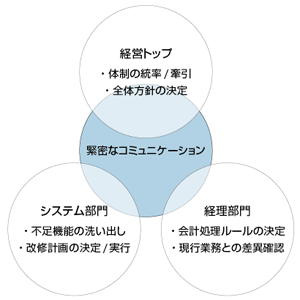
IFRSの認知度が高まってきた昨今、企業が積極的に情報収集を始めたのはよい傾向だ。しかしこの時、会計面でのインパクトは経理部門が、システム面でのインパクトはシステム部門が、というように個別に動いていてはいけない。対応プロジェクトの完遂には、経営トップ、経理部門、システム部門を含めた、全社を挙げた推進体制が欠かせない。
これまで多くの企業において、経理部門とシステム部門が深くコミュニケーションする機会は少なかったのではないだろうか。それぞれが口にする専門用語や知識は理解しにくく、互いが“不可侵領域”として一定の距離を置くように見受けられた。
だが、IFRSでは緊密な協力体制がどうしても必要だ。会計処理の方針を定めるとともに、それに伴うシステムの改修計画を立てる。個別の動きをしていては、方向性が定まらずチグハグな結果となるだろう。餅は餅屋にという「任せきり」は禁物だ。システム部門の立場に立つなら、システム面での影響度調査や改修には時間もコストもかかることを早期に理解してもらわなければならない。
もちろん経営トップの深い関与、すなわちIFRS対応プロジェクトにおける意思決定と指示のリーダーシップが必要なことは言うまでもない。
結論:情報システムへの影響度は大。一致団結が欠かせない
会員登録(無料)が必要です
- 1
- 2
- 次へ >
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






