クラウド、ビッグデータの時代だからこそ、ハードウェアを進化させなければならない−−。こんな発想のもと、米HPやIBMが半導体やメモリー素子といったレベルでの技術開発を強化している。果たしてそれはどんなハードウェアなのか。そして勝算はあるのだろうか?
「クラウド、特にIaaS(Infrastructure as a Service)がある以上、ハードウェアはコモディティ(日用品)。もはや注意を払う必要はない」−−。そう考えている人がいるとすれば、それは必ずしも正しいとは言えない。急増するデータ量や電力消費の問題が、無視できないものになることは確実だからだ。
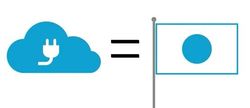 図1:世界中のデータセンターが消費する電力量は日本のそれとほぼ同じ
図1:世界中のデータセンターが消費する電力量は日本のそれとほぼ同じ拡大画像表示
何しろ、米HPによると世界中にあるデータセンター(DC)が消費する電力は世界第3位の経済大国である日本のそれとほぼ同じ(知っていましたか?、図1)。少子化や省エネ技術もあって、日本の電力消費は増加するよりも横ばいか減少と見られるが、DCは違う。世界各地で今も建設が続いている。個々のデータセンターをいくら省エネ仕様にしても追いつかない。
こうした状況をにらみ、HPや米IBMがハードウェア、それも半導体レベルの開発に力を注いでいる。HPは2014年6月に開催した自社イベントで次世代コンピュータの構想を公開。IBMは7月10日に、今後5年間で30億ドル(3000億円)をナノスケールの回路技術に投じると発表した。
いずれもまだ物語に近いが、それだけに夢があり、ITリーダーにとって知っておいて損はない。一体、どんな構想であり、どんな技術なのか、以下で紹介しよう。
HP、メモリー技術駆使による「The Machine」構想を披露
The Machine−−。HPが6月に開催したカンファレンス「HP Discover」で構想を明らかにした次世代サーバーのコードネームである。研究開発はHPの社内研究機関であるHP Labsが担っており、新しいメモリー技術や光配線技術などを用いて、既存のコンピュータの限界を打破することを狙う。具体的には「巨大なデータセンターを冷蔵庫並みのサイズにし、DCにつきまとうエネルギー問題を解消する」という。
目玉と言えるのが、「memristor」と呼ばれるメモリー技術だ。今日のコンピュータの記憶機能は、CPU並みの速度で動作するキャッシュメモリーと、電源を切ると記憶が消えるが相対的に安価なDRAMによる主記憶メモリー、電源を切っても記憶を保持する不揮発性メモリーによるSSD(Solid State Drive)や磁気記憶のHDD(Hard Disk Drive)といった階層構造になっている。
高速で安価(大容量)、しかも永続的な記憶といった相反する要求に対して、異なる特性を持つデバイスを組み合わせて対応しているわけだ。その副作用として仕組みは複雑になり、電力消費量が増大し、処理のオーバーヘッドも大きくなってしまう。
 図2:HP Discoverで披露された「Universal Memory」の試作モジュール
図2:HP Discoverで披露された「Universal Memory」の試作モジュール拡大画像表示
これに対しmemristorは、電源を切っても記憶を保持する不揮発性素子であり、キャッシュメモリーよりも高速に動作し、高集積化を可能にする。もし、ビット当たり単価を安くできれば、記憶を階層化する必要がなくなる。つまりmemristorだけで、キャッシュや主記憶、補助記憶(SSD)を置き換えられるというのがThe Machineの基本構想だ。これをHPは「Universal Memory」と称しており、HP Discoverで試作モジュールを披露している(図2)。
 図3:「The Machine」の論理構造
図3:「The Machine」の論理構造拡大画像表示
しかしシステム性能を高めるにはそれだけでは済まない。CPUとmemristor、あるいはmemristorと周辺回路を結ぶ回路も、進化させる必要がある。そのためにシリコンフォトニクス技術、つまり光ファイバーを銅線の代わりに使えるよう微細化する技術も開発する(図3)。コンピュータ内部だけではなく、当然、LANの一部も光回路で置き換える。
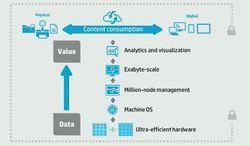 図4:「The Machine」のために開発されているソフトウェア
図4:「The Machine」のために開発されているソフトウェア拡大画像表示
メモリーや配線が変わると、OSも変えなければならない。既存のOSはキャッシュメモリーや、それよりスピードが遅いDRAM、SSD/HDDを上手く操作するように開発されているからだ。そこでHP LabsはThe Machine用に、memristorを生かし切るOSを開発している(図4)。Linuxから余分な機能を除いたOSと、AndoridベースのOSだという。
面白いのは、富士通製のスーパーコンピュータ「京」との比較だ。特定の構成で性能は5.5倍、消費電力は80分の1と見積もっている。
会員登録(無料)が必要です
- 1
- 2
- 次へ >
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






