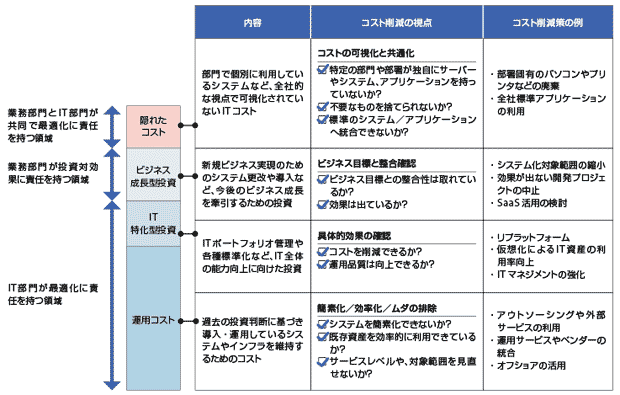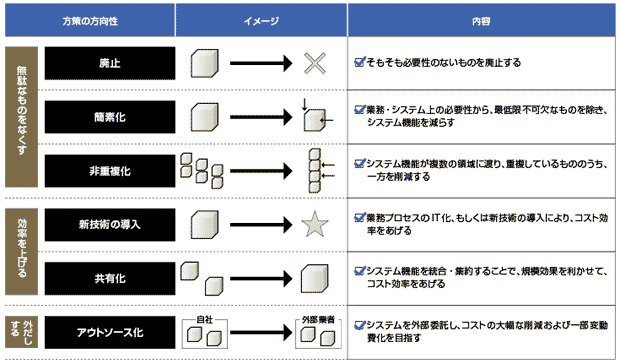EAでITのムダを排除する──複雑化したシステムは追加や変更に手間や時間がかかり、ビジネスのお荷物になる。企業のシステム部門には、「ビジネスの成長に貢献するIT」の意識を持ち、簡素化や共有化といった施策を早急に打つことが求められている。ハードやソフトといったIT資産の“見える化”は、EA実践の大きな足がかりになる。
こちらのシステムでデータ項目を1つ増やすと、連携しているあちらのシステムのデータ項目も増やさなければならない。わずかな手直しにも、多くの手間が派生する─。残念ながら、こうした悩みを抱える企業は少なくない。
このように複雑化したシステムでは、めまぐるしく移り変わるビジネスを支えることなど到底不可能である。だからといって、システムをゼロから見直す余裕は時間的にも経済的にもない。
となると、現実解は既存システムをスリム化して変化対応力を高めることだ。IT投資の全体像をとらえたうえで無駄を省くことで、システムの機動性を強化できる。本パートでは、IT投資の適正化という観点から見たシステムのスリム化について述べる。
新規開発費用だけではないIT投資の構造を知る
IT投資は、大きく4つの領域に分けられる(図3-1)。「IT特化型投資」「ビジネス成長型投資」「運用コスト」「隠れたコスト」である。
ビジネス成長型投資は、新規事業への参入や既存事業の拡大に伴う新規開発や更改など、企業の成長を直接的に支援するためのコストを指す。今後、企業が重点的に配分を行うべき投資だ。
IT特化型投資とは、既存システムの性能強化や効率化など、ITによってIT全体の能力向上を図るためのコストである。仮想化によるハードウェアの集約や、アプリケーションの社内標準化といった取り組みがこの領域に当たる。
これら2領域は、達成すべき目標に向けて新たなシステムを作り上げる戦略的投資である。これに対して、残る2領域は非戦略コストと言える。
運用コストは、過去の投資判断に基づいて導入した既存システムを“生命維持”させるために必要なコストである。隠れたコストとは、業務部門がIT部門の関知しないところで独自に導入し利用しているソフトやハードにかかる手間や費用を意味する。
こうして内訳をつまびらかにすることにより、最適なIT投資のあり方が見えてくる。「将来のビジネス拡大に備えてITのポテンシャルを維持・強化しつつ、全体の投資額を抑制する」という難題に応えるため、企業のシステム部門が目指すべきは非戦略コストのスリム化である。運用コストや隠れたコストを圧縮し、その分をIT特化型投資へと回し、さらにその結果生み出された運用コスト削減分をビジネス特化型投資に配分すればよいのだ。
ただし、戦略的投資とて聖域ではない。システムのQCD(品質・コスト・納期)を議論し、投資に見合った効果を得られそうもない新規案件は中止すべきである。さらに、業務レベルに応じた適度なサービスレベルを意識することも、過度な投資を抑制することに役立つ。
はじめの1歩は“見える化”隠れたコストをあぶり出す
非戦略コストを減らす第1歩は、IT資産の棚卸しである。社内にどのような資産を抱えているかを把握していなければ、削減策を立てられるはずがない。
「ソフトやハードの保有状況ならば、資産台帳に記載してある」─。本当にそうだろうか。資産台帳は、必ずしも社内の実態を反映してはいない。業務部門がシステム部門を介さずに導入したハードやソフトは記載されていないし、記載がある資産のなかには現在ほとんど使われていないものもあるだろう。
そこで、市販の資産管理ツールの活用を検討したい。これは、ネットワークに接続されているハードウェアや、それらの上で稼働するソフトウェアを自動検出するものである。検出結果を資産台帳と突き合わせれば、IT資産の現状を詳しく把握できる。台帳には記載があるが、ツールが検出しなかった資産は、未稼働であるということである。
こうした突き合わせは、隠れたコストの発見にもつながる。ツールが検出した資産を台帳で確認できない場合、それはシステム部門のあずかり知らぬところで導入されたことを意味する。
3つの視点でコスト削減
非戦略投資をたたく
IT資産を見える化したら次はいよいよ、「どこをどう絞るか」という施策を考えて実行する。そうした施策を抽出するには、「無駄なモノをなくす」「効率を上げる」「外に出す」という3つのアプローチが有効である(図3-2)。順に見ていこう。
「無駄なモノをなくす」というアプローチにおいては、次の3種の施策を検討する。第1は、そもそも不要なものをなくす「廃止」である。具体的には、前述したIT資産の棚卸しの結果、全く使われていないことが判明したハードやソフトの廃棄を検討する。
第2に、システムの機能を必要最低限に絞り込む「簡素化」である。導入時に比べて利用率が低下したシステムがあれば、より小さいサーバーに入れ替える。利用者数に応じて、ソフトウェアのライセンス数も見直せる。
この簡素化のアプローチでは、システム再構築も視野に入れたい。例えば、メインフレームで動いているアプリケーションをオープン化する。といっても、単純にまるごとサーバーに移行するだけでは必ずしもコストメリットには直結しない。そこで、システム全体を個別のアプリケーションに分解し、それぞれの機能や利用状況を精査する。すると、導入済みのERPやクラウドサービスが備える機能で代替できるところや、そもそも不要な機能などが見えてくる。それらを省けば、システム移行先のサーバーのサイズをぐっと縮小できる。
システムの無駄を省くアプローチにおける第3の施策は、「非重複化」である。複数のシステムが、同じデータや機能をそれぞれ個別に保持していることは非常に多い。こうした重複を排除するのである。この施策の具体例としては、マスターデータ統合や業務機能のSOAによるコンポーネント化といった取り組みが考えられる。
「効率を上げるアプローチ」におけるキーワードは、「共有化」だ。
システムのハードウェア性能は通常、月末月初といったピーク時の処理量を考慮して設計する。このため、平時のCPU利用率はせいぜい15%程度。利用可能なリソースの大部分を遊ばせているということになる。大小のシステムを組み合わせて集約すれば、こうした無駄を効率化できる。アーキテクチャが異なるシステム同士であっても、仮想化環境を構築すれば同じCPUを共有できる。これにより、サーバー保有台数や運用の手間を減らせる。
このほか、「外に出す」アプローチも考えたい。システムを、アウトソーサーに委託する。所有から利用へと舵を切るわけだ。システムそのものを社外に出してしまうことにより、運用にかかる手間やコストを削減できる。このアプローチについては、クラウドの利用も考えたい。企業内には多かれ少なかれ、他社との差異化にはつながらないものの、欠かすことのできないシステムがある。例を挙げれば、公的機関への申請システムだ。これらにクラウドサービスを採用すれば、企業は競争優位をもたらす中核システムにIT資源を集中できる。
会員登録(無料)が必要です
- 1
- 2
- 次へ >
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-