情報システムの構築では、まずパッケージ・ソフトや外部サービスの採用を検討するのが最近の主流。だが積水化学工業は電子メール、グループウェアから、会計システムまでシステムの大半を自社開発する。何がそれを可能にし、どんな利点を見い出しているのか。同社の責任者に聞く。聞き手は本誌編集長・田口 潤 Photo:陶山 勉

- 寺嶋一郎氏
- コーポレート 情報システムグループ長
- 1979年4月に積水化学工業に入社し、生産技術部において制御系システムや生産管理システムを開発。その後、積水化学工業の情報子会社アイザックで住宅事業向けエキスパートシステムの開発などを推進する。2000年6月、積水化学工業の情報システム部長に就任。組織改変により、2007年4月から現職。現在は積水化学工業の情報システム全体を統括している

- 小笹淳二氏
- コーポレート 情報システムグループ 理事
- 1988年4月、積水化学工業に入社。生産技術部でスケジューリングシステムなどの開発に携わる。積水化学工業の情報子会社セキスイ・システム・センターでの勤務を経て、2004年4月に積水化学工業 情報システムグループ異動。メインフレームの撤廃やグループウェア「Smile」の構築などの企画立案とプロジェクトマネジメントを担当している
─情報共有基盤を、すべて自社開発しているそうですね。
寺嶋:ええ、電子メールもグループウェアも自社で開発し、国内のグループ会社が利用しています。
─いまどき珍しい。パッケージ製品がたくさんあるのに、なぜリスクのある自社開発を?
寺嶋:IT革命という言葉が流行った2000年のことなんですが、メールの基盤がバラバラだったので、何とかしなければと考えたんです。
─バラバラというと?
寺嶋:当時、私は情報子会社のアイザック(2006年にNTTデータセキスイシステムズと合併)から本社に戻ってシステム部門を統括する立場になりました。ところが周りを見るとメールは定着していないし、色々な種類のグループウェアが社内に乱立していたんですよ。
─また、冗談を。2000年は、消費者のインターネット利用や企業の電子商取引(EC)が広がり始めた時期。貴社ほどの企業でメールが定着していないなんて。
小笹:それが本当に散々な状況でした。メールのアカウントが一元管理されていないので、社内に対して一斉メールも送れない状態で。
─とすると電子メールはシステム部門の管轄外だった?
寺嶋:ほとんど注力していなかったというのが正しいでしょう。
小笹:当時、アイザックとは別の情報子会社で、メインフレームの開発/運用をしていたセキスイ・システム・センター(SSC、2005年にNTTデータセキスイシステムズに社名変更)が、1アカウント1000円程度でグループ企業向けにメールシステムを提供していました。利用は必須ではなかったので、別のメールを導入するケースが多かったんです。
寺嶋:そこで、とにかくグループ全体にメールを普及させなければならないと考えて本社で予算を組み、アイザックに開発を依頼。できたWebメールシステムを、グループ会社に無料で公開しました。
OSSと開発力、ユーザー数を武器に自社開発に踏み切る
─そこですよ、不思議なのは。普通なら自社開発は大変だから、手ごろなパッケージ製品を導入しようと考える。
寺嶋:なにせ、グループ全体でユーザー数が2万人ですから、ライセンス料が無視できない金額になるんですよ。
小笹:ソフトを購入したら保守料がかかる。償却費まで考慮したら億単位のコストが発生します。
寺嶋:逆に、当社単体では2000人程度ですが、グループ全体で使えば、使い勝手のことも含めて自社開発のメリットは決して小さくないと思います。
─費用面のことを重視した?
小笹:いえ、実はアイザックにはUNIX技術者が多く、Perl言語に強い開発部隊もいたんです。それにメールシステムはオープンソース・ソフト(OSS)もありますからね。
─なるほど、ユーザー数が多いうえに自社開発できる部隊も持っていたのは大きい。でも、もともとグループ会社向けにメールシステムの事業を展開していたSSCなどから、反対意見はありませんでしたか。
寺嶋:メール事業自体は、赤字だったんです。だから、本社がSSCに支払っている費用の範囲内で作れるなら、自分たちで開発してグループに公開してしまえばいいと企画しました。
それでも「できるわけがない」、「システムが止まってメールが使えなくなったらどうするつもりだ」など、色々と言われましたよ。ただ、実はそのときすでにアイザックと話をつけてあったんです。外販も視野に入れて、良いシステムを開発していこうと。
─メールシステムはともかく、スケジュール管理や文書共有、ワークフローの機能が求められるグループウェアは一筋縄ではいかないのでは。
寺嶋:そうでもありません。開発部隊に「ちょっと作ってみてよ」と言うと、だいたい1カ月後にはプロトタイプができてきました。
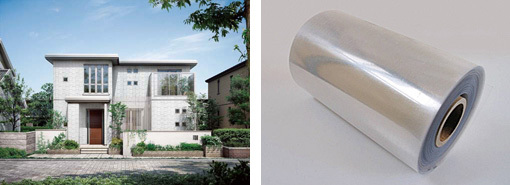
プロトタイプは1カ月で開発、機能拡張を続け使い勝手向上
─アジャイル開発でいう、1回目のサイクルがまわるということですか。
寺嶋:ええ。あくまでもプロトタイプですけれど、1カ月くらいで試せるものができてきます。
小笹:補足すると、Webメールに関しては操作性を考え、SSCが提供していたシステムと似た画面設計をするなど制約があったので、もう少しかかりました。それでも2カ月ほどです。
寺嶋:その点、グループウェアは幸か不幸か大して使われていなかったので、何でもあり。そういうときは乗りに乗って開発してくれるんです。
─それにしてもユーザー数が2万人もいるとID管理などもしっかり実装する必要がありますよね。コンプライアンス(法令順守)の観点で、退職や人事異動の際にアクセス権限を速やかに変更しなければなりません。
小笹:ディレクトリサービスを用意してあるので問題ありません。組織ごとにフォルダを用意し、各フォルダに対して権限を設定する仕組みです。人事異動の際は、対象となる社員のIDを所定のフォルダに移すだけで、新しいフォルダに設定してある権限が適用されます。
─それは、よくできている。
小笹:グループウェアが多くの企業に普及した後で作ったからですよ。結果論かもしれませんが、必要な機能要件は明解でした。
寺嶋:グループウェアは「Smile」と呼んでいるのですが、今ではCMS(コンテンツ管理システム)の機能も追加し、出社してポータル画面を表示すると、スケジュールや未処理のワークフロー、未読のメールが1画面で確認できます。最近、携帯電話から使えるように拡張しました。将来的には基幹系と連動させたいですね。基幹系の会計システムも自社開発しているんですよ。

●Next:会計システムも内製! どのように?
会員登録(無料)が必要です
- 1
- 2
- 次へ >
- データカタログ整備から広がるデータドリブン企業への変革─みんなの銀行が挑むデータマネジメント実践の軌跡(2026/01/28)
- 400万件超の商品マスターをクラウドに移行、食品流通のデジタル化を加速する情報インフラへ─ジャパン・インフォレックス(2025/12/26)
- “データ/AI Ready”な経営へ─住友電工の「グローバルデータ活用基盤」構築の軌跡(2025/12/15)
- オリンパスが挑む、医療機器ソフトウェア開発の”産業革命”(2025/10/20)
- 「データ活用宣言」を起点に広がるデータ文化─三菱電機の全社データマネジメント実践(2025/10/01)
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






