ちょっとした言葉の行き違いや誤解、錯覚がもとで要求仕様の作成に失敗すると、ユーザーの本来の要求とはかけ離れたシステムを作ってしまうことになりかねない。人間はどのような条件下で間違いを犯しやすいかを知れば、要求仕様のミスや漏れをなくしてよいシステムを作れる。
技術の進歩とともに、システムは大規模化・複雑化している。このことは、航空機や原子力プラントを思い浮かべれば容易に理解できるだろう。こうした大規模システムでひとたび事故が起きれば、その損失は計り知れないほど大きいものになる。
最新技術を駆使して作り上げた高度なシステムに、なぜ事故が発生するのだろうか。過去に起きた様々な事故を見ると、その原因のほとんどは人為的なもの、つまりヒューマンエラーだということが分かる。
航空機事故を例にとろう。航空事故を専門に追跡するPlaneCrashinfo.comによると、1950年から2006年までに起きた民間航空機の重大事故で、原因が明らかになったのは1843件。このうち、パイロットの操縦ミスは53%に上るという。それだけではない。不適切な航空管制や荷積、機体整備、燃料汚濁、言語、意思疎通の不良、操縦士間の人間関係といった操縦以外の人的ミスによる事故も7%あった。これらを合わせると、半世紀以上にわたる航空機事故の60%はヒューマンエラーが原因だったことになる(図1)。
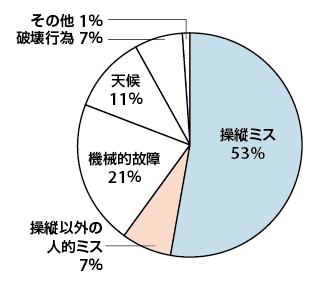
1950〜2006年に発生した航空事故の60%は操縦あるいは操縦以外の人的ミスが原因だった
(出典:PlaneCrashinfo.com)
米ボーイング社の調査でも、同様の結果が出ている。同社は1996年から2005年までに起きた自社航空機の全損事故を追跡調査した。すると、原因を特定できなかった49件を除く134件のうち、操縦ミスによる事故は37%だった。これに、不適切な航空管制や不適切な機体整備を加えると、ヒューマンエラーが原因で発生した全損事故は63%に達するという。
2001年1月に発生した日本航空機の焼津上空でのニアミス事故も、ヒューマンエラーが原因だったと言われている。航空管制官が、2機の旅客機の便名を読み間違えたのである。空中衝突防止装置が接近を感知して警告を発したが、パイロットはそれを無視して管制官の指示に従ってしまった。その結果、衝突こそ直前で回避できたものの、43人の乗客や客室乗務員が負傷した。専門家の間でしか使われていなかったヒューマンエラーという言葉がマスメディアでさかんに取り上げられ、私たちの耳に入るようになったのはこの事故がきっかけだった。
このように、技術の粋を集めた航空機においてもヒューマンエラーが発生する余地は大きい。要求仕様を作成する場面でも、ヒューマンエラーは当然起こり得る。どんなに優れた要求工学技術や豊富な経験を駆使しても、間違いは発生する。読み違いや勘違い、書き違いなど、人間が要求仕様に害をなすことは多い。人間は、間違いを犯す生き物なのである。
そこで今回からは、これらの問題を引き起こす人間について考える人間工学に視線を移す。どうすれば要求仕様を作成する際のヒューマンエラーを減らし、より良い問題解決策を導き出せるのかを解説する。
人間工学的アプローチとは
人間工学とは、人間が使用する道具・機械・システム、あるいは人間が行う作業や活動を、人間にとって好ましくなるように「作り出していく」ための学問分野や実践活動である。
人間工学の歴史的な流れをひも解くと、2つの流れに行き当たる。1つは、欧州中心のエルゴノミクス(Ergonomics)である。これは労働科学的研究をベースに、疲れず快適に作業するための作業条件や方法、環境を研究する学問である。
人間工学のもう1つの流れは、米国を中心とするヒューマンファクター(Human Factors)と呼ぶ学問だ。こちらは、作業のムリ・ムダ・ムラを減らすための動作研究をもとにしており、人間が機械を使用する際の信頼性や安全性を向上するための科学的管理法の追求に主眼を置いている。
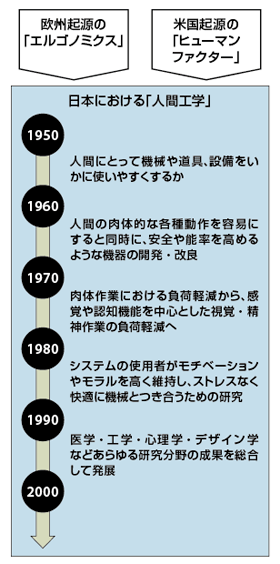 図2 日本における人間工学の歩み
図2 日本における人間工学の歩み1950年ころに日本に登場し、肉体作業の負荷軽減から視覚・精神作業の負荷軽減へとテーマを変遷させてきた
欧州と米国という異なる地域で生まれ育ってきたエルゴノミクスとヒューマンファクターはその後、次第に融和。統一的な学問とみなされるようになり、日本にも伝わった。日本に人間工学という概念が登場したのは、1950〜60年ころである(図2)。当時、人間工学は機械や道具、設備といった物理的な環境を人間にとっていかに使いやすく、働きやすくするかという視点から追求された。
60〜70年代、工業技術が急速に発展して作業の自動化やシステム化が進むと、人間工学は人間の肉体的な各種動作を容易にして安全や能率を高めるような機器の開発・改良に応用されるようになった。
その後、作業の自動化やシステム化が進むにつれて、人間工学は肉体作業における負荷の軽減から、感覚機能と認知機能を中心とした視覚・精神作業の負荷軽減へと目を向けるようになった。これに伴い、人間の知覚や感覚による機器の評価・改良が行なわれるようになった。
情報化時代の幕開けとなった80〜90年代には、情報をいかに正確に理解し評価・判断するかが人間工学の中心的な関心になった。具体的には、システムの使用者がモチベーションやモラルを高く維持し、ストレスなく快適に機械とつき合うための研究や応用がさかんに行われた。
このように、人間工学の研究テーマは、当初の人間の運動機能を主にした肉体作業への負荷の軽減から、感覚機能と認知機能を中心とした視覚・精神作業の負荷軽減へと比重を移してきた。そして現在、人間の行動や認知特性、評価技術などに関する人間工学の知見は、医学・工学・心理学・デザイン学などあらゆる研究分野の成果を総合して発展している。
ヒューマンエラーを分類する
人間工学的アプローチにおいて、ヒューマンエラーは行動の視点と情報処理プロセスの視点からそれぞれ分類される。
ヒューマンエラーは、行動の類型によって「省略エラー」「誤処理エラー」「不当処理エラー」「順序エラー」「タイミングエラー」の5つに分類できる。省略エラーとは、必要な作業や処理を省略してしまうエラーである。誤処理エラーは、誤った作業や処理を実行してしまうエラーのこと。不当処理エラーは、不当なタスクやあるいは行動を行うエラーだ。このほか、作業遂行の順序を間違えてしまうのが順序エラー、所定の時間や時期に作業を実行しないのがタイミングエラーである。
ヒューマンエラーは、情報処理プロセスという視点からも分類できる。誤認や見落とし、状況認識の誤りなどの「知覚エラー」、考え違いや勘違い、判断間違い、計算違いなどの「認知エラー」、物忘れや記憶違いなど「記憶エラー」、誤操作やタイプ間違いなどの「運動エラー」、会話や連携の間違いや指示抜け、命令間違いなどの「コミュニケーションエラー」の5タイプである(図3)。
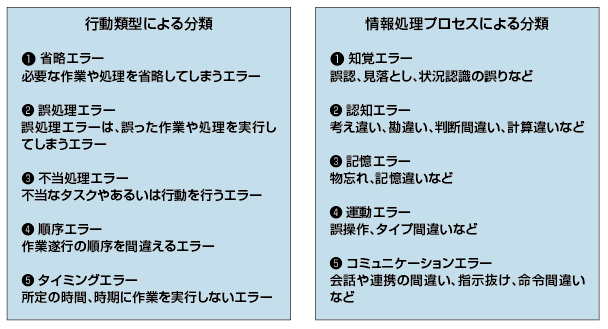
行動類型や情報処理プロセスによる分類が代表的だ
みなさんにも、いくつか身に覚えがあるのではないか。こうした人間の特性によって引き起こされる要求仕様の間違いには、大きく2つのパターンがある(図4)。1つは、問題のとらえ方を間違えるパターンだ。これは、要求仕様を作成する際に要求者の言葉を取り違えてしまう、要求者が意図したイメージと異なるイメージを抱いてしまう、といったことだ。そもそもの出発点から間違えているため、その後も誤った方向に作業が進んでしまう。
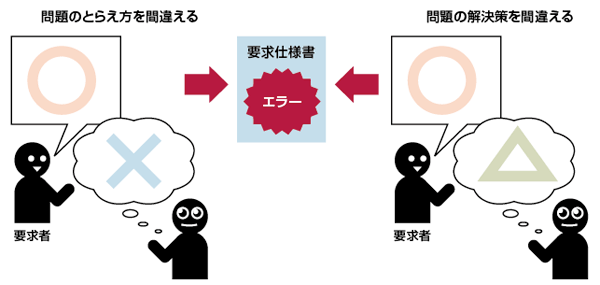
言葉の取り違えによる誤解や解決手段の選択ミスは、時間やコストの無駄や要求者の不満につながる
もう1つは、問題の解決策を間違えるパターンである。これは、要求者の意図を正しく理解して問題を正確に把握していたが、問題を解決する手段を誤るパターンだ。解決策が不適切だと、要求を満たすために費すコストや期間が無駄にかかる、あるいは、要求者にとって不都合はないが満足のいくものではなかった、という望ましくない結果を招くことになる。
会員登録(無料)が必要です
- 1
- 2
- 次へ >
- 要求仕様作成における最大のコツ─機能の2割をカットする:第14回(2009/11/02)
- システム仕様を数式に変換─Z言語で要求仕様を厳密に記述する:第13回(2009/10/02)
- 業務の粒度やアクターの役割を明確化し、システムのふるまいをUMLで表現する:第12回(2009/09/04)
- スケッチ、設計図、プログラミング言語UMLの利用法を再確認する:第11回(2009/08/06)
- ブレーンストーミング、KJ法、NM法、マインドマップ─発想法のエッセンスを理解する:第10回(2009/07/06)
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






