1990年代なかばから、企業の経営環境が大きく変化している。きっかけになったのは、インターネットの普及である。インターネットが出現する以前、市場の変化は現在よりはるかに緩やかだった。企業は、市場の変化を見てから組織を変更し、対応するだけの余裕があった。この時期、ITはあくまでも組織を支援するための道具にすぎなかった。
1990年代なかばから、企業の経営環境が大きく変化している。きっかけになったのは、インターネットの普及である。インターネットが出現する以前、市場の変化は現在よりはるかに緩やかだった。企業は、市場の変化を見てから組織を変更し、対応するだけの余裕があった。この時期、ITはあくまでも組織を支援するための道具にすぎなかった。
しかし、インターネットの普及がビジネスのスピードを劇的に速めた。
近年、新製品が発売されるやいなや、その品質や使い勝手について口コミ情報がインターネット上に溢れるようになった。消費者は、インターネットを通じて製品を比較し選択する。消費者の本能である比較して選択する行為が、瞬時に行われるのである。このような市場に対して、従来のように組織変更で対応しようとしても間に合わない。組織とは人間の集合であり、人間の動作は遅いからだ。
このため、変化の激しい市場に対しては組織ではなくITで対応するようになった(図1)。その代表例がB2Cであり、B2Bである。近年は、さらに進化してオークションサイトのようなC2B2Cのビジネスモデルも出現した。
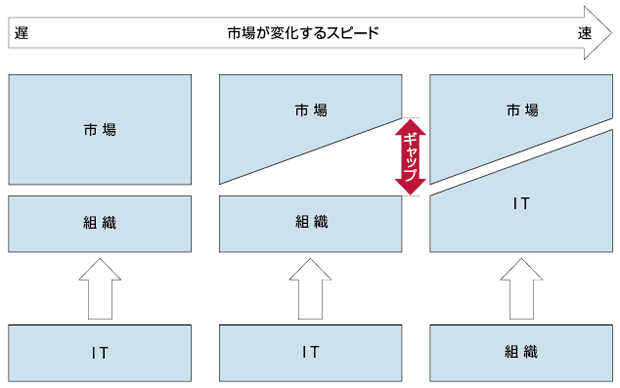
このようにITが市場とじかに接するようになれば、システムに対する要求は厳しくなる。当然ながら、要求仕様の作成にはこれまで以上の精度が求められる。万が一、要求仕様をしっかり詰め切れないとその後の開発が予定通り進まず、システムの稼働が遅れるからだ。システムの稼働が遅れればそれだけ市場への対応も遅れ、企業全体の収益に影響を及ぼしかねない。
要求仕様をつくるコツ
ここで、筆者がこれまでのシステム開発経験から得た「要求仕様を作るコツ」を紹介したい。
プロジェクトが失敗する原因は、機能の詰め込みすぎにあることが多い。もちろん、限られた予算と開発期間の中でよりよいものを作ろうとするのは、システム担当者として自然な欲求である。
しかし、機能を詰め込めばよいというわけではない。あれもこれもと欲張ると、機能間の整合性を確保しにくくなるし、開発期間も圧迫する。「機能を2割カットする」。これが要求仕様を作る際の最大のコツである。
具体的にはまず、必要な要求機能を洗い出して一覧に書き出す。次に、1つひとつの要求機能に優先順位をつけていく。優先順位を付け終わったら、順位の高いもの順にソートする。そして、優先順位の低い機能から2割をカットするのである。カットする際は、機能同士の整合性を担保しておくことに注意したい。
要求機能をカットすることで、機能間の整合性を確保しやすくなるから、開発期間も大幅に短くできる。こうして予定より早くシステムを作り上げれば、余った期間でカットした2割の機能の一部を追加開発することも可能である。
ここで、「ユーザー部門から上がってくる要求に優先順位をつけるのは難しい」「カットする機能をどう判断すればよいのか」という疑問を解消しておこう。
まず、ユーザーが要求する機能には「あると便利な機能」と「なければ困る機能」の2種類があることを知っておきたい。この2つには、大きな差がある。
あると便利な機能は、真っ先にカットする対象になる。その機能がなくても、たいして不便でない場合が多いからだ。実際、「あると便利だから」というユーザー要求は、単なる個人的な趣味に近い場合がある。そうした機能が提案されたら、「なければ困るのか」と問えばよい。多忙なIT担当者に、個人的趣味につきあう暇はないはずである。
一例を挙げよう。ある企業でシステムを再構築することになった。IT部門の担当者が機能を棚卸した結果、バッチプログラムの約40%が帳票プログラムであった。そこでこの担当者は現場に出向いてヒアリングを実施した。ヒアリングの要点は、帳票の要不要を判断することである。現場から1つひとつの帳票の必要性について合理的な説明と裏付けがないものは、新システムでは出力しないことにした。その結果、新システム稼働後に「帳票がなくて困る」といったクレームを受けることはほとんどなかったそうである。
会員登録(無料)が必要です
- 1
- 2
- 次へ >
- システム仕様を数式に変換─Z言語で要求仕様を厳密に記述する:第13回(2009/10/02)
- 業務の粒度やアクターの役割を明確化し、システムのふるまいをUMLで表現する:第12回(2009/09/04)
- スケッチ、設計図、プログラミング言語UMLの利用法を再確認する:第11回(2009/08/06)
- ブレーンストーミング、KJ法、NM法、マインドマップ─発想法のエッセンスを理解する:第10回(2009/07/06)
- 現実解に固執せず自由に発想し独創性の高い解決策を生み出す:第9回(2009/06/04)
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






