日本の大手SI企業は、クラウド中心の今日においても旧来のソフトウェア製造業のビジネスモデルから抜け出せず、多重下請け構造や偽装請負などの問題が生じやすい。これは発注側の事業会社がITを丸投げし、SI企業も安易なビジネスに甘んじて技術力向上を怠った結果でもある。ERPの導入・刷新の失敗例からも、事業会社の経営層、自社のITを担う情報システム部門の主体性が問われている。
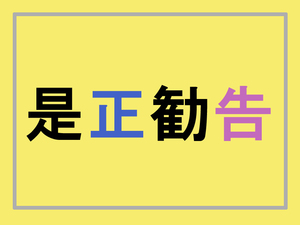
日本の代表的なメインフレームメーカーは、クラウド時代になってSI会社に転身した。SI=システムインテグレーションと言えば聞こえはいいが、大半のSI会社の実態はソフトウェア製造業だ。請負で完成責任を負ってソフトウェアを製造するならまだしも、品質トラブルを起こすと大変なので、準委任契約で責任を逃れたりするところも多い。
ソフトウェアの品質問題は、元請け会社が下請け会社を使う多重下請け構造にも由来する。その構造は建設業界と似ているが、かなり以前に本コラムで指摘したように、許認可産業である建設業とは根本から異なる。建設業における下請会社は29分野の許可業種の専門性を持った会社であり、建設プロジェクトにおいてそれらの会社の情報は責任者と共に開示される。品質を担保する法的な仕組みの1つである。
許認可産業ではないソフトウェア産業にはそれがない。ソフトウェアの下請会社は技量レベルも責任者も開示されることはなく、実態はブラックボックスである。それをよいことに下請けや孫請け、ひ孫請け会社の中には、社員のスキルや実務経験を偽って素人同然の人材を元請けのプロジェクトに送り込むところが増えている。
責任放棄の丸投げ体質がSI会社をダメにした
しかも時々、労働基準監督署の指摘があるように、偽装請負で未熟な技術者を労働派遣させたりしている。人材不足が深刻化する中、一定以上のスキルや実務経験を持つ人材を採用できないことが背景にあるようだ。こんな環境で作られるソフトウェアに信頼性などなく、元請けが高額な料金で担保する構造が成り立っている。
では、そんなSI会社にだれがしたかと問われれば、答えは発注側である事業会社の経営者だ。経営層から丸投げされた情報システム部門は、「大手に任せておけば楽」とばかりに、自ら基本設計もしないで要件定義から外注したりしている。大手SI会社の担保力に期待して高額な請負料金を容認し、経営トップと同じようにほぼ丸投げする。
大手SI会社もその慣行に甘んじていて安易なビジネスに走り、高度な技術者育成やソフトウェア開発に関わる研究開発に投資してこなかった。だから、例えば生成AIの新しい知見も出てこない。日本発の技術が生まれたり生み出したりすることもなく、海外技術の寄せ集めに頼っている。経済産業省が「2025年の崖」などと煽るものだから、システム更新の需要だけは増えただろうが、存在したのは崖ではなくいまだに越えられない壁のようだ。
デジタル活用だ、DXだという前に、事業会社の経営トップはビジョンと戦略を持っていなければならない。経営者が「ITは素人」と自認するのは許されない時代である。技術を事業やビジネスにどう活用するかを考えるのは経営者の仕事だ。実装や実現を担うのはシステム部門だが、要求定義だけして要件定義から先を外注しようとするシステム部門を改革するのも経営者の役割だ。
大手SI会社より、自社の技術者がコードを書いている中堅のソフトウェアメーカーのほうが信頼性は高い。だから、自立性が高い事業会社のシステム部門は中堅・中小の開発会社をよく活用する。切磋琢磨で双方が成長する。
さらに言うと、日本よりベトナムなどのソフトウェアメーカーのほうが、人材育成も請負ビジネスもアグレッシブな面がある。日本の商習慣に馴染むために、当初はSI会社の下で請けていた仕事を直接、事業会社から請けるケースも増えてきている。
●Next:事業会社のシステムへの主体性の欠如がもたらす大きな損失
会員登録(無料)が必要です
- 1
- 2
- 3
- 次へ >
- 「2025年の崖」はどうなった? DXレポートから7年後の実態を検証する(2025/12/24)
- 生成AIで進化するサイバー空間の“悪意”、どう対処するか?(2025/11/26)
- ヒューマノイドの時代が確実にやってくる(2025/10/28)
- 「越境」のすすめ─CIOは専門性の境界を越える「総合診療科医」であれ!(2025/09/25)
- 年初発表の「2025年世界10大リスク」を振り返ってみる(2025/08/28)
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






