前回まででビジネスプロセスがどういったものか理解していただけたと思います。ではBPMとは何でしょうか?BPMとは、事業戦略を効果的・効率的に実現する為に、ビジネスプロセス(BP)を継続的に改善してゆく手法です。ではどのように改善してゆくのでしょうか?改善するためには対象となるビジネスプロセスを明確に理解しておかねばなりません。そうでないと問題となっている部分、改善すべき部分がわからなくなってしまうからです。
2. BPMとは
1) ビジネスプロセスの整理
ここでもう少し詳しくビジネスプロセスについて整理をしておきたいと思います。前回(第2章前編)の図1では、以下の注文処理を対象としたビジネスプロセスを図示しました。
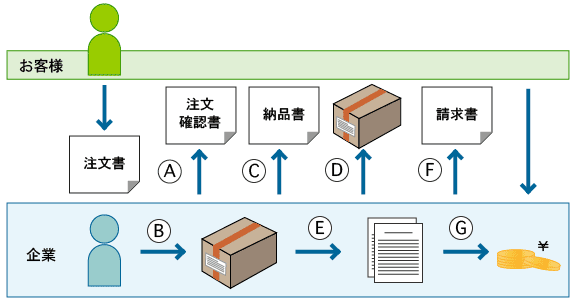
- A.お客様から注文書をいただく。+お客様に注文確認書を送る
- B.社内で商品の手配と発送の手続きを取る。
- C.お客様に納品書をお送りする。
- D.お客様に商品が届き検収していただく。
- E.社内で売り上げ計上の手続きを取る。
- F.お客様に請求書をお送りする。
- G.お客様からの入金を確認する。
このビジネスプロセスは、「見積」「与信」「受注」「出荷」といった作業から構成されます。ビジネスプロセスを構成する作業はサブプロセスと呼びます。
次に、ビジネスプロセスを構成するそれぞれのサブプロセスについて、順序、内容、関係する組織、人、物といった観点から、それを構成する要素を以下のように明確にしておきます。
- 開始条件:サブプロセスが開始されるきっかけ。「受注」であれば「注文書」の受領が開始条件になります。サブプロセスがそのビジネスプロセスの最初のサブプロセスであれば、この開始条件はビジネスプロセスの開始条件と同一になります。
- 入力:サブプロセスにおいて、そのサブプロセス外からもたらされ、サブプロセスの遂行に必要となる情報あるいは物。例えば「受注」においては「注文書」が入力となります。入力がない場合もあります。
- 入力元:入力が送られてくる元。通常、人や組織、あるいは別のサブプロセス(先行サブプロセス(後述))。「受注」においては「顧客」が入力元です。
- 出力:サブプロセスの結果としてそのサブプロセス外に渡されるもの。「受注」においては「出荷指示」となります。
- 出力先:出力の渡し先。別のサブプロセス(後続サブプロセス(後述))、あるいは人や組織など。「受注」においては「出荷」が出力先となります。
- 作業内容:サブプロセスで「出力」を得るために行う一連の作業の内容。「受注」においては「注文書」から「出荷指示」を作成するための作業となります。
- 作業リソース:上記の作業内容を行う担当者や組織。「受注」においては「営業管理部門」となります。どの部門や担当かのみでなく、人数、作業予定時間も明確にしておきます。
- 先行サブプロセス:当該サブプロセスを実行するための前提となる先行するサブプロセス。「受注」においては「見積」となります。先行サブプロセスは必須の場合とそうでない場合があります。例えば「与信」は「受注」の先行サブプロセスですが、見積もりの金額が一定額以上でなければ実行されないこともあります。
- 後続サブプロセス:当該サブプロセスの実行を前提とする後続のサブプロセス。「受注」においては「出荷」となります。上記先行サブプロセスの場合と同様に必須の場合とそうでない場合があります。
以上のように各々の作業内容・作業順序などを明確に捉えることで、ビジネスプロセスが誰にでも分かるように「可視化」されます。またサブプロセスも、さらに粒度の小さい一連の作業として捉えることができる場合があります。これに対しても上記と同じ整理作業を繰り返して、入れ子構造になったビジネスプロセスとして整理することができます。このようにして全体から詳細へと対象範囲を区切りながら順次BPMに取り組んでゆくことができます。
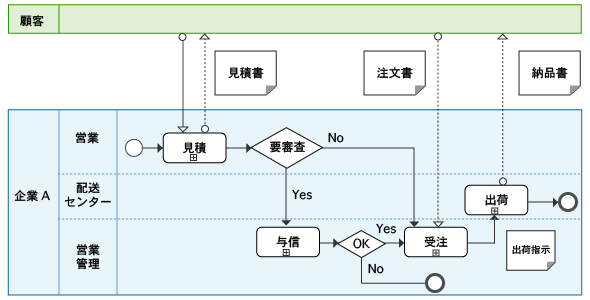
2)BPMとは
ここから再びBPMの説明に戻りたいと思います。
「ビジネスプロセス:その1」にある「B.社内で商品の手配と発送の手続きを取る。」の場面を再度想定してください。皆さんは管理職の方々だと思いますので、営業事務などの担当のかたに、「この注文の発送手続きお願いね」で済んでしまうのではないでしょうか?ではその人がお休みだったときはどうしますか?しかも急ぎの注文だった場合に。だれか替わりの人に頼みますか?自分でやりますか?でもだれもやり方を知りません。今日中に手続きしないと他社に頼むとお客様には言われています。
「B.社内にて商品の手配と発送の手続きを取る。」は前述のようにビジネスプロセスを構成するサブプロセスとして捉えることができるものですから決まった進め方はあるはずです。しかしその進め方が、担当者以外の人にも理解できるように文書などに整理されていなければ業務に支障をきたしてしまいます。
皆さんの会社にも仕事を熟知したベテランの方々がいらっしゃることと思います。その方々が退職した後でも滞りなく業務が進められるような仕組みを持っていますか? それを可能にするためには業務をビジネスプロセスとして捉え、それを明確化した上でマニュアルや規程として文書化し、組織の中で共有してゆく必要があります。これが「可視化」と「共有化」です。
では実際に業務をビジネスプロセスとして捉えて整理して行く「可視化」を皆さんの会社で行う場面を考えてみてください。この作業はBPMの第一歩です。業務の中に存在する作業を洗い出し、作業の相互の関連やそれぞれの作業業務の順序、必要なリソースなどを明確にして行きます。
そのとき「可視化」を担当する人はいろいろな業務の担当者に話を聞いたり、業務規程などの文書を調べたりすることになります。多分そのときにいろいろな疑問にぶつかることと思います。「何でこの順序で作業を行うのだろうか?」「似た作業を何回か行っているが、同じやり方に統一できないのだろうか?」などです。
もちろん、それぞれに理由や経緯があることと思いますが、単にいままでのやり方を踏襲してそうなっているだけかも知れません。もっとよい作業の順序があるかも知れないことに皆さんは気づくはずです。つまりビジネスプロセスには改善の可能性が多分にあるということです。重複している作業や無駄な作業をなくし、業務の効率化を図ることができます。これが「最適化」です。また、ビジネスプロセスの中の類似した作業については、皆が同じやり方でできるように統一してゆきます。こうして、一連の作業を皆が同じ進め方でできるようにします。これが「標準化」です。
このようにBPMでは業務をビジネスプロセス(前述したようにそう捉えることができるものを対象としますが)として整理することで、誰にでもわかるように「可視化」・「最適化」し、「標準化」して、その上で「共有化」を進めて行きます。こうして重複した作業や無駄な作業をそぎ落として行くことができるのです。またこの活動は一過性のものではなく、継続してゆかなければ意味がありません。ビジネスは刻々と変化します。それに合わせてビジネスプロセスも変化する必要があるからです。
会員登録(無料)が必要です
- 1
- 2
- 次へ >
- BPM実践事例3:三技協─「業務構造」「プロセス」「マニュアル」の可視化/共有化で企業変革(2011/05/20)
- BPM実践事例2:リクルート─「じゃらんnet」を支えるバックオフィス業務の効率化(2011/05/06)
- BPM実践事例1:日産自動車─業務をいかに標準化するか(2011/04/22)
- 総論:理論から実践へ、事例で学ぶ取り組みのポイント(2011/04/15)
- BPMの今後の方向性・可能性(第6章)(2009/10/09)
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






