次々とヒット商品を生みながら成長を続ける小林製薬(本社:大阪府大阪市)。競争の激しい市場において経営の屋台骨となっているのが、キメ細かい生産管理・原価管理を具現化するシステムである。国内グループ工場への導入、さらに、中国・米国拠点への展開と、息つく間もないプロジェクトを完遂した原動力は、現場のリーダー達の熱意だ。過去20年に及ぶ取り組みを振り返る。
1997~2006年
より緻密な原価管理を目指し生産管理システムを構築
OTC医薬品(一般用医薬品)や日用雑貨品の製造販売を事業の柱とし、健康で快適な生活の創造をビジネスのビジョンに掲げる小林製薬。トイレ用芳香洗浄剤の「ブルーレットおくだけ」や、額に貼り付けられる利便性で大ヒットした「熱さまシート」など、印象的なネーミングも相まって日常生活に馴染み深い製品は数多い。「“あったらいいな”をカタチにする」のブランドスローガンに象徴されるように、消費者の潜在的なニーズをいち早く発見し、斬新なアイデアを次々に製品化していく開発力こそが同社の最大の強みと言えるだろう。2016年3月期の連結決算でも、18期連続の増益かつ過去最高益を達成するなど同社の業績はきわめて好調だ。
だが、良い製品を作りさえすれば収益増につながるほど甘い世界ではない。現在、市場に流通している小林製薬の製品は1000アイテムを超えるが、OTC医薬品や日用雑貨品といった製品はもともと利幅が薄いうえに、ヒット商品が生まれたら生まれたで必ずといってよいほど競合他社から類似品が登場してくる。熾烈な価格競争に打ち勝つことができなければ、収益を上げるどころか大変な損失を招きかねないのだ。
 小林製薬 グループ統括本社 業務改革センター IT部で部長を務める大坪吟氏
小林製薬 グループ統括本社 業務改革センター IT部で部長を務める大坪吟氏そこで小林製薬が徹底的に取り組んでいるのが生産管理・原価管理の高度化である。「その起点となったのが、1997年の生産管理システムの導入でした」と振り返るのは、小林製薬 グループ統括本社 業務改革センター IT部で部長を務める大坪吟氏だ。
システム導入以前の原価管理の水準はというと、原材料の仕入諸掛を例にとれば、工場ごとに、生産しているすべての品目で按分していたという。当然のことながら、これでは緻密な原価管理は不可能だ。「ある製品を1個作るのにどれだけのコストがかかっているのか、現実の数字を掴まないことには、製造プロセスのどこに無理や無駄が発生しているのか分析することができず、コストダウンのためのアクションを起こすことはできません」と大坪氏。そこで、品目直課の個別原価計算への転換を図るための新システムを導入することとなり、その基盤として採択したのが東洋ビジネスエンジニアリング(B-EN-G)のMCFrameだった。
もっとも、1997年当時のMCFrameが主にカバーしていたのは生産管理で、原価管理に関する機能は手薄だった。それでも小林製薬がMCFrameを選んだ理由は、Manufacturing and Communication Frameworkの名が示す「フレームワークコンセプト」にある。MCFrameは業務機能を再利用可能な「部品」として実装する形を採っており、共通フレームワーク上に部品を追加していくことで効率的にカスタマイズすることができる。追加開発されたユーザー独自の業務プロセスは、あたかもオリジナルの機能であるかのようにMCFrameの基本機能部分とスムーズに連携できる点を評価した。
「外資系ベンダーの製品を含めて当時のERPはどれも原価管理機能は総じて貧弱で、結局はアドオンするしかありませんでした。ならば、自分たちの思い通りの原価管理の仕組みを作り込めるフレームワークの方がよいと考えたのです」と大坪氏は語る。こうしてB-EN-Gとのパートナーシップを通じて完成したのが、「BOSS(Business Operation Standard System)」と呼ぶ同社の独自システムである。
2006~2008年
基盤を再ビルドアップした新生産管理システムが完成
改善を繰り返しながら運用してきたBOSSだが、カットオーバーから10年近くが過ぎると、さすがにこれ以上カスタマイズを重ねるにも限界が見えてくる。
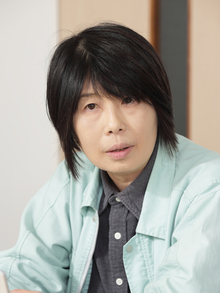 小林製薬 製造戦略部 製造システムグループの担当課長を務める中野久美子氏
小林製薬 製造戦略部 製造システムグループの担当課長を務める中野久美子氏小林製薬 製造戦略部 製造システムグループの担当課長を務める中野久美子氏は、「インフラ部分もアプリケーション部分もつぎはぎの増築を重ねた状態になっており、例えば営業管理システムと連携するインタフェースなど、バージョンアップさえままならない部分もありました」と振り返る。
そこで小林製薬はBOSSの全面刷新を決断。本部および大阪工場、グループ会社として展開している富山小林製薬、仙台小林製薬、愛媛小林製薬の各工場から生産管理の担当者が集まって、新たなシステムの仕様策定に向けた協議を開始した。中心となった課題は大きく次の2つである。
1つは本部とグループ各社の間で行われている取引への対応だ。グループ会社の工場が生産した製品を本部が仕入れる、グループ会社に対して本部が原材料を有料で供給するといった、これまでのBOSSには組み込まれていなかった業務プロセスを新システムに実装するものだ。「単に受発注処理をカバーするのではなく、本部側の在庫や販売予測などの数字を工場側からも参照できるようにすることで計画的な生産を可能とし、より精度の高い原価管理に役立つ仕組みにしたいと考えました」と中野氏は語る。
もう1つは多言語、多通貨のサポートだ。BOSSの構想時にはほとんど考える必要がなかった海外取引がその後急速に進み、新システムでの対応が急がれたのである。従来からのBOSSを継承しつつ、これらの新機能をいかなる基盤に実装するのが効率的なのか――。小林製薬はいくつかのソリューションを比較検討したが、最終的に残ったのはやはりMCFrameだった。
「MCFrameに新たに登場した原価管理パッケージには、私たちがカスタマイズで実装してきた業務ノウハウの一部が標準機能として備わっています。ベンダーのサポート体制も重要な評価ポイントであり、私たちの業務と課題、これまでの取り組みを熟知しているB-EN-Gのコンサルタントが、引き続きプロジェクトマネジメントを担当してくれることになりました。これらを総合的に考慮したとき、やはりMCFrameを基盤にするのが最善と判断したのです」(大坪氏)。
こうして2006年10月から2008年4月までの約1年半をかけて構築したのが「N-BOSS(New Business Operation Standard System)」である。国内全製造グループの統合マスター、医薬品MES連携、外部OEM/購買先とのWEB-EDIなどの機能も備え、小林製薬のビジネスの屋台骨を支えるシステムへと大きく進化を遂げた。
会員登録(無料)が必要です
- 1
- 2
- 3
- 次へ >
- データカタログ整備から広がるデータドリブン企業への変革─みんなの銀行が挑むデータマネジメント実践の軌跡(2026/01/28)
- 400万件超の商品マスターをクラウドに移行、食品流通のデジタル化を加速する情報インフラへ─ジャパン・インフォレックス(2025/12/26)
- “データ/AI Ready”な経営へ─住友電工の「グローバルデータ活用基盤」構築の軌跡(2025/12/15)
- オリンパスが挑む、医療機器ソフトウェア開発の”産業革命”(2025/10/20)
- 「データ活用宣言」を起点に広がるデータ文化─三菱電機の全社データマネジメント実践(2025/10/01)
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






