新しいことにチャレンジする際には、知識や見識に加え、肝に据えて行動する力、すなわち「胆識」が不可欠となる。ゴールを生々しくイメージし、そこを起点に日々の行動に落とし込む習慣を身に付けるのだ。実行によって体験できる真実を1つひとつ吸収することは、必ず自己成長の肥やしとなる。
「成功の反対をいまだに失敗だと思ったりしていませんか?」─。
この問いは、多くのベンチャー起業家の育成に尽力した経営学の先生が、経営者を集めてのパーティーで登壇した際に第一声で語ったものだ。そして、こう続けた。「経営の世界では、成功の反対は『何もしない』ということなんです」。
つまり、挑戦することの重要性を説いたのだ。これは、経営者のみならず、ビジネスパーソンにしても未知の世界に飛び込む習慣を身に付けることで、多くの気づきが得られることを暗示している。
今回は、常にチャレンジしようとする意識とモチベーションとの関係を紐解き、挑戦意欲を高めるためのポイントを提示したい。
モチベーションは人のOS
仕事で成果を上げようとする時、人は何を拠り所とするだろうか。これまで積んできた経験、頑張って身に付けた知識やスキル、社内外に形成してきた人脈などを挙げる声は多いことだろう。もちろん、こうした資産はとても大切だが、あなた自身の仕事への姿勢が「ピッと背筋が伸びたもの」でないと、一向に有効活用されないことを忘れてはならない。私は、この姿勢こそモチベーションだと考えている。
パソコンに例えるなら、人のモチベーションは、動作の基本を司るオペレーティングシステム(OS)のようなものだ。一方で「経験」「知識/スキル」「人脈」に相当するのはアプリケーションソフトである(図1)。
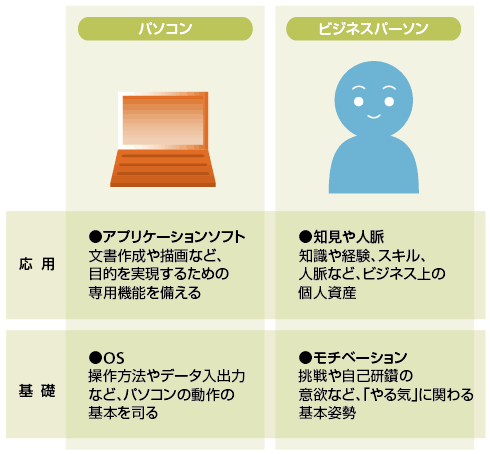
このアプリケーションソフトの領域は、世の中がどんどん移り変わる中ではブラッシュアップが欠かせない。つまり、経験も知識も人脈も常に最新版にバージョンアップすることを心がけなければならないのだ。
もっとも、どんなに最新のソフトを積んでいても、OSのバージョンが古いとせっかくの機能を十分に発揮できないのはパソコンも人も一緒である。つまり、モチベーションが低めで安定してしまうと、新しい知見も多様な人脈も、今の仕事に生かせず、"宝の持ち腐れ"となってしまう。私たちが新しいことにチャレンジしようとするためには、OSのバージョンアップ、つまりモチベーションを高め安定に保つ努力が不可欠となる。
モチベーションを高く保つ努力を重ねていると、その意識や行為自体が学習によって血肉と化し、たとえ下がりそうな事象に出くわしても跳ね除けられるようになる特性がある。自動アップデート機能が働くのだ。
「構想する意識」を備える
では、どのような心がけが必要となるのか。知人のオーナーシェフが興味深い話をしていたので紹介しよう。
「新しいメニューを開発する際のポイントは構想力だ」というのが彼の主張である。さらに、「素材やレシピなどに気を取られると、やる気は高まらない。お皿に盛り付けられた出来上がりの作品をしっかりとイメージすることが肝要」とも付け加えた。
仕事の結末(成果)をイメージすると思わずワクワクしてしまう。その一方で、やらなければいけない作業工程や打ち合わせの量などに意識が割かれるとやる気が萎える…。こんな経験に心当たりがある読者も少なくないだろう。
構想力とは「未来の完成品(成果)を論理的に予測する力」と言われているが、心理学的には「先行体験を基にして、現実に感覚していない新しいイメージを思い浮かべる能力」と言っている。いずれにしても、私たちが新たなチャレンジを模索する際にまずやるべきことは、その挑戦の方法論を考えるのではなく、挑戦の結果もたらされる成果をいち早く脳裏にイメージすることである。それらを“身体化”するためには、仕事に限らずスポーツや遊びにおいても、上手くいったときのゴールの姿から今に遡る思考訓練を日ごろからすることである(図2)。我々はとかく「木を見て森を見ない」アプローチをするものであり、十分な注意を払わなければならない。
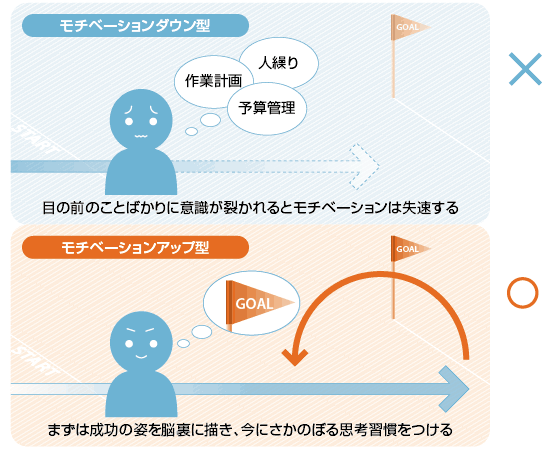
構想力のシンボリックな事例として、こんな話がある。ディズニーワールドの開園式。すでに他界していたウォルト・ディズニー氏に代わって出席していた夫人に対し司会者が、「ご主人がこの場をご覧になれればよかったですね」と問いかけた。すると彼女は、「この事業を始めようと心に決めた時、彼にはすでに今日の様子が見えていたのよ」と答えたそうだ。ゴールがイメージできている人は強いのである。
行動力を伴った見識を養う
構想する意識が備わり、しっかりとゴールセッティングができたら、挑戦のための組み立てが必要だ。その際に意識するべきなのが、「知識・見識・胆識」である(図3)。
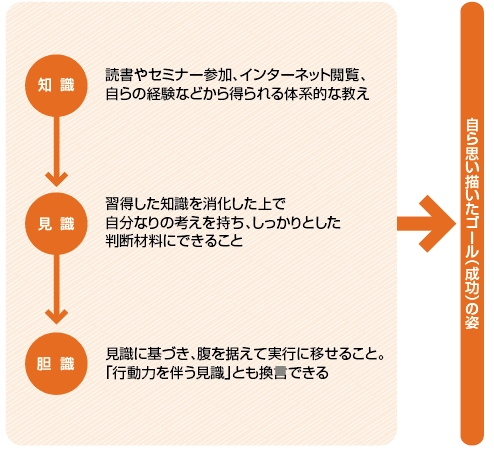
「知識」とは、ご存じの通り、本を読んだりセミナーに出たり、インターネットを調べたりといった行為を通じて得られる教えを指す。次の「見識」とは、そういった知識や経験を通して学んだことを自分なりに消化して、ある課題に対して自分の意見をしっかり言うことができ、判断ができることである。
ここまでで物事へのスタンスが定まるわけだが、まだ挑戦にはつながらない。ここから必要となるのが「胆識」である。胆識とは、腹を据えて行動すること、実行することだ。つまり、行動力や実行力を伴う見識こそが胆識なのだ。知識や見識が浅い中での行動は、軸がぶれやすく、成果が出にくいことがよくある。また、人によってはチャレンジが知識や見識のレベルで止まっても満足してしまうこともある。
胆識が備わっているか否かは、何か大きな問題に直面した時にすぐ見極めることができる。日頃は偉そうなことを言っていながらも大切な時に右往左往してパニックになってしまう人が、あなたの周りにも見受けられるのではないだろうか。この人たちは見識までの域を出ず、その場は凌げるのであるが、後で振り返ると真の力が透けて見えてしまう。いわゆる「評論家タイプ」であり、よく勉強しているので論は立つものの、「彼(彼女)が今までやり遂げたことは?」と周囲に聞いてみると「?」となる。そんなタイプの人が意外にも組織の中で「優秀な人」と評価されているケースは少なくない。
どうしたら「胆識」を備えることができるのか。言葉としての答えは至極単純で、決意を持って"評論家"ではなく"実行家"になるしかない。多くの知識とフレッシュな見識からリスクを想定し、腹を据えるのだ。先の読みにくいこの時代、実行によって体験できる真実を1つひとつ吸収することが自分を成長させると思い続ける。腹に据えた挑戦は、必ず自己成長の肥やしとなる。上司が部下の行動を支援する際も、「部下の胆識を高めている」ことを意識して真剣にサポートしなければならない。別の視点から見れば、胆識を促進するためには、いつも知識をインプットできる情報ルートを確保し、見識を高めるための人脈を構築することが不可欠だとも言える。
相手起点のコミュニケーション
「知識・見識・胆識」を支えるのは、言うまでもなく、他者とのかかわり合い、コミュニケーションである。私たちがビジネスにおいて新たな挑戦を試みるとき、周りの人の支援なくして成就することはまずあり得ない。その一方で、人間関係の悪化などからモチベーションが下がり、挑戦欲求が萎えてくることもよくあることだ。
こうした背景から、世の中にはコミュニケーションスキルにかかわるビジネス書や研修が数多く存在し、一定の人気を誇っている。これらは同じことを異なる次元で表していることが多く、中心を成すコミュニケーションの要は、何よりも「相手の立場に立てるかどうか」である。他者の知恵や発想に耳を傾けようとしない独りよがりの挑戦は、成功確率を下げる結果になることは言うまでもない。
先日、「部下の挑戦意欲を削がないコミュニケーション」の事例として、あるメーカー研究所の責任者が次のような話をしていた。
「新製品開発においては研究員1人ひとりのモチベーションが最も重要。だからこそ社内外の知恵を如何に上手に集めるかを支援しています。彼らとのコミュニケーションでは、"No Because"よりも"Yes But"の話法を心がけています」。
これはつまり、会話のキャッチボールを促進する工夫だ。「このような企画を考えてみたのですが…」と部下が相談に来たシーンを思い浮かべてほしい。様々な統計データを見るまでもなく、自分の経験からも難しい開発だと分かっていても、頭から相手の意見を否定せずに、まずはYesと答えて、それからButを使って理由を伝えるのである(図4)。
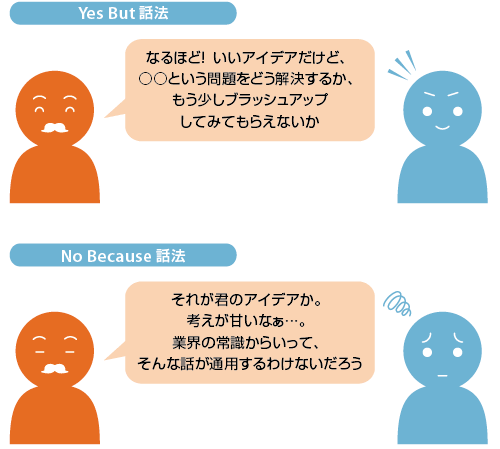
「それは、誰が考えても無理だろう。ダメな理由は○○だからだよ」と切り出されるよりも、「なるほどね。そういう着眼はあるんだけど、でも、○○を考えると難易度は高いよなぁ。何か打開策はあるだろうか」と指摘された方が、次の挑戦意欲にきっとつながるはずだ。
小さな挑戦の連続が推進力に
ただ単純に「何事にも果敢に挑戦しよう」と掛け声高らかに叫ぶだけでは不十分であり、実は周到な準備が必要である。その準備の過程にこそ、モチベーションを高めに安定させる力があるわけである。
日々変わらず、与えられた環境や指示されたことだけをこなすだけでは、モチベーションは決して高く維持できない。とにかくいつも、「もっと時間を短縮できないか」「他にもいい方法があるはずだ」などの問いを、自分にぶつけることから始めよう。その問いを解くことが小さな挑戦であり、行動することなのである。この小さな挑戦を繰り返すことを私は、「チャレンジトリップ」と呼んでいる。
これまでの繰り返しになるが、その旅を成功させるのは研ぎ澄まされたイメージ構想力、とにかく成し遂げようとする胆識、そして旅の途中で出会う人々との「良きコミュニケーション」なのである(図5)。
挑戦という名の旅は、必ずしも成功を約束されたものではない。想定外の経済環境や社内の状況、さらには自分の未熟さで上手くいかないことも多々ある。けれども、このことだけは確実に言える。旅に出ている間、つまり挑戦し続けている間は、高いモチベーションでいられる。そして、旅の終わりには必ず人間としての「成長」が約束されるのである。皆さんも是非、大空に向かって最初のステップを踏み出してほしい。ボン・ボヤージュ!
- 大塚 雅樹 おおつか・まさき
- JTBモチベーションズ 代表取締役社長
- 1961年東京都生まれ。86年、明治大学法学部法律学科を卒業しJTB(日本交通公社)に入社。91年、社内公募で市場開発室に異動しワークモチベーションの研究を開始。93年、JTBモチベーションズ設立と同時に出向、2004年に代表取締役社長に就任し現在に至る。著書に「やる気を科学する」(河出書房新社)、「明日の出社が楽しくなる本」(インデックスコミュニケーションズ)など。
- ブランド意識とモチベーション─今こそ組織への誇りと愛を育みモチベーションを高める(2009/08/10)
- チーム内の異質性を保ち、知恵のぶつかり合いを促進する(第10回)(2009/07/08)
- 悩み多きリーダーが次世代のリーダーを育てる(第9回)(2009/06/08)
- オーダーメードの育成戦略で部下をやる気にさせる(第8回)(2009/05/12)
- 目指せ!褒め名人─表面的な褒め言葉は逆効果、水面下のプロセスを称賛し続ける(2009/04/07)
- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】
- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】
- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】
- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】
- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】
-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは
-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法
-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート
-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは
-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」
-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」
-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





